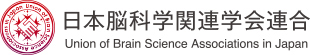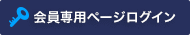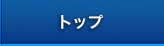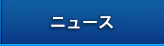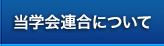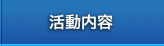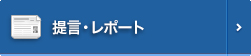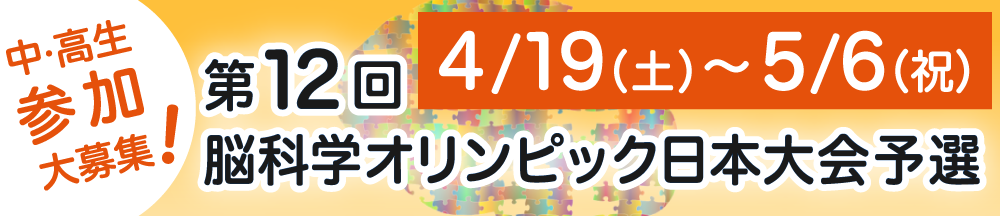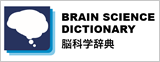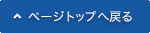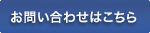第6回産学連携諮問委員会
【日本脳科学関連学会連合 第6回産学連携諮問委員会 議事録】
日時
2025年8月3日(日)14:00-15:50
場所
TKP品川カンファレンスセンター カンファレンスルーム6A(対面)とオンライン参加
参加者
現地参加:池田和隆(委員長)、大隅典子、尾崎紀夫(副委員長)、加藤忠史、上野太郎、菊地哲朗、守口善也、住吉太幹(WG4,TF1)
オンライン参加:池田昭夫、伊佐正、後藤純信、白尾智明、竹島多賀夫、藤原一男、石山健夫、武見充晃(WG4,TF2)、萩原一平(副委員長)、平田幸一、松元健二
オブザーバー出席者:
岡野栄之(脳科連代表)
欠席者
阿部修(副委員長)、梅田聡、小澤一史、川合謙介、工藤與亮、黒田輝、齊藤延人、田中謙二、中込和幸、林(高木)朗子、松田哲也、平田晋也、本田学(WG4,TF4)
(以上敬称略)
議事
1.活動報告
2.今後の予定
3.その他
議事内容
会議に先立ち、今期第7期の岡野代表、加藤副代表より、それぞれ挨拶があった。池田和隆委員長より議事進行について説明があった。
1.活動報告
1)WG1 政府の健康医療戦略に関する検討グループ グループ長 尾崎紀夫委員
日本脳科学関連学会連合と日本学術会議との連携:2026年G7での声明に関して次の通り説明があった。今回、2026年度議長国フランスアカデミーからG7で共同声明に関する連携の提案があり、学術会議としてはこの提案に対して全面的に賛同し、学術会議「脳とこころ分科会」、「神経科学分科会」、日本脳科学関連学会連合、国立精神・神経医療研究センターと連携していくことが報告された。
連携する背景には、日本学術会議の今期(第26期)骨子の中に「学術の発展のための各種学術関係機関との密接なコミュニケーションとハブとしての活動強化」、「ナショナルアカデミーとしての国際的プレゼンスの向上」があり、今後、日本学術会議では国際連携と様々な学協会連合との連携を行っていくことが説明された。
2)WG2 日本学術会議での未来の学術振興構想に関する検討グループグループ長 伊佐正委員
伊佐委員が遅れて出席のため、池田和隆委員長より代理で未来の学術振興構想について次の通り説明があった。3年前に構想の募集があり脳科連より2つ構想を提出したが、それを1つにまとめたものがグランドビジョンとして採択された。現在はこの構想を10月1日までに改訂する意思表明をしており、他にも脳科学関連の構想があるためそれらにある程度合わせてより強力なものにしていくことが説明された。その後、伊佐委員より次の通り説明があった。未来の学術振興構想とは別に文科省のロードマップがあり、そこへ掲載されると大規模学術フロンティア促進事業として予算化されることがあるため、今後、脳科連としてもロードマップへどのように対応していくか議論していきたいとの説明があった。
3)WG3 バイオマーカーの産学連携開発制度の検討グループ グループ長 池田昭夫委員
前グループ長阿部修委員より引継ぎ今後検討することとして、神経免疫においても産学連携で疾患単位の点でもアルツハイマー病の抗体療法を画像化して効果を観察。MRIにしても機能面だけでなくMRIのトラクトグラフィーとのインテグレーションの可能性を高めていく。電気生理的にはAIの立場からの脳波の自動判読、それに関連してニルス、MEGがあり、モダリティの違いはあるがそれらをまとめてバイオマーカーとして方向性を示していくことが報告された。
4)WG4 臨床研究規制や治療法認可制度の検討グループ グループ長 池田和隆委員長
・TF1グループ長 住吉委員よりTF1分散型臨床試験(DCT)推進活動について次の通り説明があった。分散型臨床試験とは研究施設に訪問する必要のない臨床試験のことで、例えばビデオや遠隔医療による訪問、デジタルヘルステクノロジーなどがあること、また今回AMEDの「精神疾患領域の臨床試験における評価バリアンス軽減に関する研究開発事業」に採択されたこと、それに伴いDCT-TFのメンバーを拡大し製薬企業8社、グローバルCRO5社が新たに参画することが報告された。今までに2回の会議を経て産学連携を通して活動を深めて行き、数年後の目標として「遠隔評価システムを実装した治験による薬事承認申請に向けた提言」を目指すことが説明された。
・TF2グループ長 武見委員よりTF2デジタルブレインの活動について次の通り説明があった。TF2はニューロテクノロジーの倫理に関するルールメイクについて活動していること、背景にはOECDやユネスコといった国際機関がニューロテクノロジーの倫理に関するルールメイクを進めている中で国内のキーパーソンや日本の意見をどのように出していくかといった課題があることが説明された。その中で大きな活動成果として、新たな国際標準戦略の文書にニューロテック・ブレインテックが明記されたことが報告された。また産学の意見を集約してどのような標準作りをしていくかを検討する必要があったため、第48回日本神経科学大会ランチョンセミナーを開催し企業からの意見も交えた体制ができたことや、今後の課題としては基礎研究と標準化の理解を深めるために知財専門部からニューロテクノロジーの標準化に関する講演を調整していくことが報告された。
・TF3グループ長 池田和隆委員長よりTF3ドラッグリポジショニング推進活動について次の通り説明があった。他疾患向けの既存薬を精神神経疾患へ適用するドラッグリポジショニングの有効性や様々な問題により実際社会では使用されていない状況について説明があり、今後はドラッグリポジショニングに関する状況、特にドラッグリポジショニングに携わった企業が赤字にならないような法制度などの調査を継続する。具体的には、既存薬の新適応承認に特化した新たな申請区分を創設し審査手続の簡素化・迅速化を図るとともに、知的財産権およびデータ独占に関する特例措置を検討するなどである。また、開発インセンティブ・薬価制度の改革、社会的認知の拡大と臨床現場の意識改革、学術界・産業界・行政の連携強化が重要であり引き続き国に提言していきたいと報告があった。
・TF4グループ長 本田学委員の代理として萩原一平委員よりTF4インフォメーションメディスン推進、情報医学・医療推進活動について次の通り説明があった。インフォメーションメディスンの定義の説明があり、中でもヘルスケア分野を包含し情報で介入し、健康に生きる力を引き出しWell-beingな状態を維持改善することに注目が集まっていることが説明された。去年成立したISO25554では日本が主導の上、Well-beingがISOの規格になり日本の職域では「心の健康」と生産性やワーク・エンゲイジメントとの関連が指摘されるようになりその重要性は高まっていることが報告された。一方で簡易生理計測デバイスの一般的な課題が挙げられた。今後は健康経営・ブレインヘルスケアに関する情報収集と課題抽出・検討をしていくことが説明された。
5)WG5 製薬協会員会社脳科学連携の検討グループ グループ長 石山健夫委員
製薬協会員会社との連携活動や脳科連と製薬協の橋渡しの支援を目的としてできたTFであることや、現在メンバーに変更があり製薬企業5社6名が参加していることが説明された。2024年に文科省「脳神経科学統合プログラム」が始まり、その中で産学官コンソーシアムを作る構想がありWG5で議論し、その後脳科連と製薬協での議論を文科省や製薬協会へつなげていったことが報告された。
2.今後の予定
池田委員長より、今後も産学連携諮問委員会として、情報を共有して活動していくことが報告された。また、この後開催の講演会について説明があった。
3.その他
特になし
以上