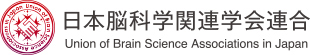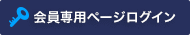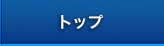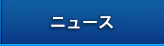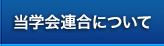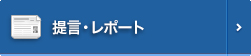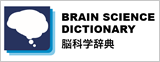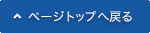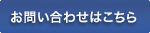===========================
脳科連バイマンスリーメールマガジン 2025年9月号(No.32)
http://www.brainscience-union.jp
===========================
日本脳科学関連学会連合会員学会・連携法人会員及び評議員の皆さま
❏今月のコンテンツ
・脳科連連携法人一般会員のご挨拶文:小原 喜一(小原医科産業(株)代表取締役)
・第29回リレーエッセイ:才藤 栄一(日本ニューロリハビリテーション学会理事長)
・第12回脳科学オリンピック結果ご報告:奥村 哲(脳科学リテラシー委員会委員長)
・産学連携諮問委員会主催第4回講演会ご報告:池田 和隆(産学連携諮問委員会委員長)
・活動報告(8月〜9月)
・事務局だより
【脳科連連携法人一般会員のご挨拶文】
脳科連連携法人一般会員 小原医科産業株式会社 小原 喜一
私共は大きく2つの仕事をしております。1つはマウス・ラット・サル用の行動実験機器の開発・製造・販売で、研究者の皆様と直接お話をして仕事をいただいております。もう1つは実験動物用の飼育器材の一部である自動給水システム・部品の輸入・開発・製造です。いずれも実験動物に関わる内容で、携ってもうすぐ60年になります。
小原医科産業(株)は1966年に私の父である小原 喜代三が創業しました。彼は生物学に興味があり、医者になりたいとも思っておりましたが、経済的な理由で大学に進学することができず、高等学校卒業と同時に働き始めました。それでも医学・科学に関係していたいと考え、医学・理化学商品を扱う商社に勤め、日本全国の病院・大学などの顧客を訪問しておりました。
喜代三の父つまり私の祖父は生まれつき心臓に不具合があり、子供のころから絵の修業をし絵描きとなりましたが、若くして他界しました。よって喜代三は祖父つまり私の曽祖父に育てられました。曽祖父は商店を営んでおり、亡くなるとき喜代三に小原商店を継いで欲しいと希望しました。その商店は医学・科学とは全く関連のない商品を取り扱っておりましたが、喜代三はこれを継ぎ、商社勤めで得た知識と人脈を元に商売を始めました。
ところで1950年代には実験動物用のげっ歯類は農家の副業として育てられており、品質は粗悪だったようです。大陸で良質な実験動物を利用してきた安東 洪次博士と田嶋 嘉雄博士が実験動物研究会(現在の日本実験動物学会)を設立し、実験動物の飼育環境改善と良質な実験動物の提供という理念を主張しました。そしてそれを具現化するべく、安東先生と安東研究室所属の野村 達次先生が、文部省直管の財団法人実験動物中央研究所(現在の公益財団法人実中研)を設立しました。そして小原医科産業は野村先生のご依頼で米国ジャクソン研究所からマウスの輸入の仕事を請け負います。私共が実験動物に関わることになる始まりです。実中研が日本クレア(株)を作る前後のことです。
SPF動物が作出されるようになった1970年くらいから、日本国内でも動物実験施設の建設が始まり、特にブリーダーや民間企業研究施設において、自動給水システムが求められるようになりました。当時米国ではすでに自動給水システムが利用されており、小原医科産業はこれを輸入し普及することに尽力しました。現在は米国からの輸入だけでなく、日本独自の給水システムを開発・製造しております。このことから、私共は飼育器材の業界団体である日本実験動物器材協議会の初期からのメンバーであり、現在は代表を務めております。
一方、実中研は1966年に医学部門を設立し、薬物依存の分野で世界的に注目されていた柳田 知司博士を迎えました。小原医科産業は柳田先生から行動実験についての手ほどきを受け、その後に柳田先生から群馬大学の田所 作太郎博士をご紹介いただき、行動実験装置の開発・製造・販売に着手しました。日本でも薬物依存が問題になり、世界的に抗認知症薬の開発が盛んになるなど、行動実験の需要が急激に高まったのでした。欧米からの輸入機器が主流でしたが、研究者の目的に沿った実験装置の開発・製造を承り、実験できるまで責任を持つというスタイルで仕事をいただけるようになりました。抗認知症薬の開発が世界的に頓挫した頃、二代目である私 小原 喜一が働き始めまして、お客様にご指導をいただきながら現在に至ります。今でも仕事の半分は開発を伴う内容でして、皆様の研究の一助となることを願っております。
池田 和隆先生のご推薦により連携法人一般会員となりましたが、私共は少ない人員で切り盛りしており、今のところ役立たずで恐縮です。科学に関わる方々が集まって日本の行末を考え、ロビー活動を含めて行動なさることで、皆様が自由な研究をなさる環境が整い、研究者を目指す若い方が増えることを期待しております。
【第29回リレーエッセイ】
日本ニューロリハビリテーション学会 理事長 才藤 栄一
日本ニューロリハビリテーション学会理事長の才藤 栄一です。
この小文は、日本ヒト脳マッピング学会理事長・宇川 義一先生からのバトンを受けてのエッセイです。ここでは、日本ニューロリハビリテーション学会(Japanese Society for Neural Repair and Neurorehabilitation: JSNRNR, https://www.fujita-hu.ac.jp/~rehabmed/JSNRNR/) の存在理由を、私なりの視座から述べ、脳科連の皆さまにご紹介したいと思います。以下、リハビリテーションは「リハ」と略します。
本学会は、World Federation for NeuroRehabilitation (WFNR) の national society として、2010年1月30日に設立されました。会員は現在384名で、リハ科医、脳神経外科医、神経内科医、さらに多様なリハ関連専門職から構成され、年次学術集会を通じて知の交流を重ねています。次回、第17回学術集会は、2026年2月27日(金)・28日(土)、名古屋・ウインクあいちにて、国立長寿医療研究センターの加賀谷 斉先生が主催されます。
本学会の使命は三本の柱から成り立っています。すなわち、①神経系疾患に対するリハ医学的探究、②神経科学のリハ医療への応用、③神経科学とリハ医学の相互作用です。
①は、いわゆる「疾患別リハ」という区分法において神経系疾患のリハはその中心的領域となりますから、リハ医学のサブスペシャリティ的課題です。②は、神経科学の進歩がリハ治療をどのように変えていくかを追究する課題です。両者はいずれも正統的かつ必然的な課題といえます。しかし、私が最も心惹かれるのは③、すなわち「相互作用」の探究です。
科学的理解は原則として還元主義を基盤とします。しかし、神経系の機能と、その作動の結果として現れる活動や行動は、あまりに複雑なシステムであり、部分の集積としては把握しきれない全体性を有しています。リハ医学はその逆説を体現しています。すなわち、「機能や構造の結果」である活動が、再び「機能や構造の原因」として作用するというウロボロスの蛇のような因果の循環を、治療体系に取り込んできたのです。さらに神経系そのものもまた、進化の過程において「成功した活動」に応じて変化を重ね、その複雑さを築き上げてきました。その意味で、生物は「目的を有する人工物」にも似た、「環境からの結果を取り込み、リモデリングする存在」といえるでしょう。近年登場した進化生物学とゲノムサイエンスの統合的な説明枠組み(例えば、ニール・シュービン 2021)は、この因果的相互作用の解明に資するものと期待されます。
ここで鍵となるのが「階層性」です。神経系の生理学的階層性と、リハ医学における活動階層性をいかに接続するか――この問いこそ、本学会の「相互作用」という課題の核心に他なりません。
ハーバート・サイモン(1996)の言葉は示唆的です。「コンピュータは具体的なハードウェアとして存在しながら、その魂はむしろプログラムに見いだされる。」この比喩は、神経系の生理学的階層性がどのようにハードとソフトに分担され、それらが活動階層性へと反映されるのかを考える端緒となります。学習などソフトウエアが担う部分と活動入力との関係をいかに観察し、その汎用性をどのように探るべきか――この点は大きな関心事です。さらにサイモンは「科学の発展が『宙に浮いた摩天楼』の建設のごとく可能なのは、各階層レベルにおける行動を規定するものが、その直下のレベルにおけるごく単純化された特性にすぎないからである」と述べました。神経科学とリハ医学の相互作用にこの階層性の指針をいかに組み込むことができるのか。相互作用理解への挑戦が、私たちの学会に託されていると思っています。
本学会の存在意義は、単なる研究領域の集積ではありません。それは、神経科学とリハ医学という異なる階層の知を媒介し、両者の往復運動を通じて新たな臨床の方向づけを創ることにあります。その営みを具体的に形にしていくことが、私たちの責務です。
次号、第30回のリレーエッセイのバトンは、日本アルコール・アディクション医学会 神田 秀幸先生にお渡しいたします。
【第12回脳科学オリンピック結果ご報告】
脳科学リテラシー委員会委員長 奥村 哲
第12回脳科学オリンピック日本大会は、4月末から5月上旬にCBTで行われた予選参加者75名のうち、上位10名を予選通過者とし、7月に日本代表と最終順位を決めるファイナル試験を対面で行いました。
その結果、以下の順位が確定いたしました。なお、この入賞者10名は、7月24~27日に新潟で開催されたNeuro2025(第48回日本神経科学大会)に招待され、期間中に表彰式が行われました。また副賞として、「小説みたいに楽しく読める 脳科学講義」(大隅典子著、羊土社)が授与されました。
入賞者のうち、希望者には玉川大学脳科学研究所、新潟大学脳科学研究所などのラボ見学の機会が与えられました。日本脳科学関連学会連合(脳科連)・脳科学リテラシー委員会は、今後も、入賞者の皆さんに大学・研究所の研究室見学などや、脳科学関連学会主催の公開イベントへの招待などの機会を作って参ります。
第12回脳科学オリンピック日本大会の最終順位は以下の通り(敬称略)です。
佐藤 美樹(1位:日本代表)、小澤 美咲(2位)、伊佐 賢杜(3位)、佐藤 凜奈、北尾 和佳(2名が同率で4位)、吉井 葵(6位)、于 杭立(7位)、森本 嶺大(8位)、甲斐 悠真(9位)、付 聖宣(10位)
これまで、資金面を含めて本大会を温かくご支援くださってきた脳科連会員学会の先生方(特に入賞者全員を大会にご招待してくださった日本神経科学学会の先生方)、ラボ見学、学会イベントなどにご協力いただいた(あるいはこれからお引き受けいただく)大学・研究施設等の先生方に深く御礼申し上げます。
なお、「脳科学オリンピックの寄付金募集」を今年度も10月上旬より行う予定にしております。改めて事務局よりご連絡いたしますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。
【産学連携諮問委員会第4回講演会(第3期健康・医療戦略を踏まえた脳科学研究の方向性
:大隅 典子講師)ご報告】
産学連携諮問委員会委員長 池田 和隆
産学連携諮問委員会では、産学連携に関連する専門家から学び、ご助言いただく機会として、クローズドなオンライン講演会を企画してきています。第1回として国立がん研究センター理事長(当時研究所長)の間野 博行先生にご講演いただいた際は、以前のメルマガでご紹介いたしました。第2回は、当時製薬協会長でいらした岡田 安史エーザイ株式会社取締役(当時代表執行役COO)、第3回は、医薬品医療機器総合機構(PMDA)理事長の藤原 康弘先生にご講演いただき、多くのご教示とご助言をいただきました。そして今年度より国で第3期健康・医療戦略が始まったことから、健康・医療戦略参与をお務めの大隅 典子脳科連運営委員(東北大学経営戦略本部アドバイザー・東北大学大学院医学系研究科教授)に、今回の第4回講演会でご講演いただきました。大隅先生は第3期戦略を構想する時期に、国の健康・医療戦略推進専門調査会の委員をお務め下さっていて、この第3期戦略について脳科学者の中で最もお詳しい先生です。産学連携諮問委員会では、5つのワーキンググループ(WG)で活動していますが、そのWG1がまさに国の健康・医療戦略への反映を目指すWGで、尾崎 紀夫WG長の企画、進行で今回の講演会が開催されました。
ご講演では、第3期健康・医療戦略の推進体制と概要と第3期日本医療研究開発機構(AMED)の体制と推進概要をご紹介いただくとともに、その中での脳科学の位置づけについて解説していただきました。講演でご紹介いただいた主な関連ウェブサイトは以下です。
第26回健康・医療戦略参与会合(2025年7月2日開催)参考資料4
(第3期健康・医療戦略の推進体制について)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/sanyokaigou/dai26/sankou4.pdf
第26回健康・医療戦略参与会合(2025年7月2日開催)参考資料2-3
(第3期健康・医療戦略概要)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/sanyokaigou/dai26/siryou2-3.pdf
日本医療研究開発機構(AMED)第1回説明会(令和7年4月24日)理事長説明資料
(日本医療研究開発機構(AMED)第3期の概要)
https://www.amed.go.jp/content/000145890.pdf
第3期医療分野研究開発推進計画には以下の8つの統合プロジェクト(PJ)が設定されています:①医薬品PJ、②医療機器・ヘルスケアPJ、③再生・細胞医療・遺伝子治療PJ、④感染症PJ、⑤データ利活用・ライフコースPJ、⑥シーズ開発・基礎研究PJ、⑦橋渡し・臨床加速化PJ、⑧イノベーション・エコシステムPJ。感染症以外は、がんも含めて疾患領域は計画概要に記載されておらず、脳神経疾患についても記載がありません。また、疾患領域に関連した研究開発としては、上記の8つの統合PJを横断して、がん、難病・希少疾患、ライフコースの3つが示されており、脳科学は主に「ライフコース」の中とのことです。第1期、第2期と比べて、脳科学が明示されていない点は注意しておく必要があるとのことです。第2期では、健康・医療戦略推進専門調査会では、大隅先生と神庭 重信先生の2名の脳科学者が委員を務めてくださっていましたが、第3期では脳科学の専門家が委員に含まれていない点も心配な点です。脳科連内でしっかり対策を立てていく必要があると思われます。一方、第3期戦略では、出口思考が強められているので、産学連携諮問委員会の役割はさらに高まることと思われます。
第4回の講演会では、脳科連運営委員の大隅先生にご講演いただいたこともあり、新しい情報を得るだけでなく、今後の脳科連の活動方針を検討する重要な機会にもなりました。今後も脳科学における産学連携推進に繋がる講演会を企画して参りますので、ご講演いただきたい講師の先生をお知らせ頂ければ幸いです。また、ぜひ産学連携諮問委員会の活動をご理解、ご支援いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
【活動報告(8月~9月】
・令和7年度第1回産学連携諮問委員会および第4回講演会(8月3日)
・令和7年度第1回将来構想委員会(8月3日)
・第33回評議員会(メール審議9月10日~9月19日)
【事務局だより(主に会員学会事務局向け)】
・脳科学オリンピックの寄付金募集期間は10月上旬に募集開始予定です。
ご協力をお願いいたします。
・評議員の変更がございましたら、事務局までご連絡をお願いいたします。
・メールマガジン内容へのご意見やお問い合わせは、貴学会の事務局経由でお願いします。
(代理発送)
日本脳科学関連学会連合事務局
office@brainscience-union.jp
URL:http://www.brainscience-union.jp/
〒113-8657 東京大学農学部内
TEL: 03-5842-2210 / FAX: 03-5842-2237