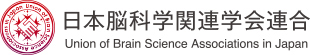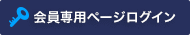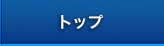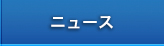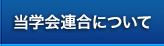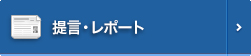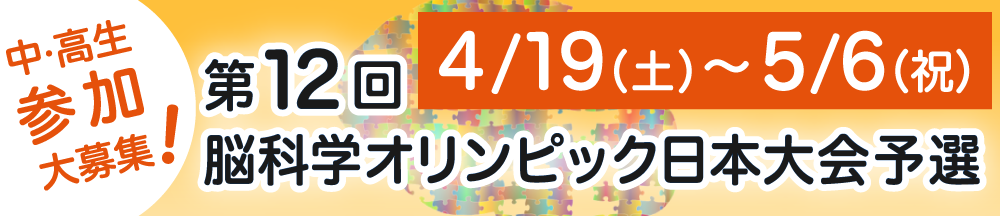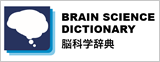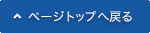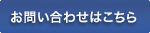ブログアーカイブ
| 2022年6月27日 | ||
第2回 脳科学将来構想委員会を掲載しました。 |
||
| 2022年6月27日 | ||
2022年 第2回 脳科学将来構想委員会 |
||
【2022年第2回 脳科学将来構想委員会 議事録】日時2022年6月5日(日曜日)10:00~12:00 場所オンライン会議(Zoom) 出席委員:阿部 修、池田 和隆(副委員長)、磯田 昌岐、礒村 宜和、岩坪 威、梅田 聡、大塚 稔久、尾崎 紀夫、勝野 雅央(副委員長)、加藤 忠史、田中 沙織、花川 隆(委員長)、林 朗子、村山 正宜、柚﨑 通介、和氣 弘明 議事1.趣旨説明 2.神経科学領域に対する大型予算措置の現状について代表及び各担当委員より説明。 3.ポスト革新脳・国際脳事業について 以 上 |
||
| 2022年6月27日 | ||
2022年 第1回 脳科学将来構想委員会 |
||
【2022年第1回 脳科学将来構想委員会 議事録】日時2022年3月21日(月-祝日)15:00~17:00 場所オンライン会議(Zoom) 出席委員:池田 和隆(副委員長)、磯田 昌岐、岩坪 威、梅田 聡、大塚 稔久、尾崎 紀夫、勝野 雅央(副委員長)、田中 沙織、花川 隆(委員長)、林 朗子、村山 正宜、柚﨑 通介、和氣 弘明 委員以外の出席者:影山 理研CBSセンター長、岡野 栄之、松田 哲也、伊佐 正(代表)、斉藤 延人(副代表) 議題1.理研CBSの将来計画 2.今後の脳科学研究の推進について 3.その他 以 上 |
||
| 2022年6月8日 | ||
会員学会年次大会情報を更新しました。 |
||
| 2022年6月8日 | ||
第25回評議員会議事録を掲載しました。 |
||
| 2022年6月8日 | ||
第25回評議員会 |
||
【日本脳科学関連学会連合 第25回評議員会 議事要録】日時令和4年4月21日(木曜日)(メール配信日)~5月12日(木曜日)(回答締切日) 参加者評議員 全90名 議事:(審議事項)(1)現代表、副代表、運営委員の任期の延長 審議の結果:(1)現代表、副代表、運営委員の任期の延長 ・(ご意見1)提案そのものには賛成ですが、本来ならば、6月30日の2か月前までに選挙の公示をするという規約があるなかで、今のタイミングでの任期延長の提案、 (2)庶務幹事、会計幹事職の設置 (3)COI管理委員会の設置について ・(ご意見2)COI管理委員会の設立の趣旨には全面的に賛同致します。しかし、「連合代表が指名する」という点では、手続きに瑕疵があるのではないかと思います。本委員会は、 ・(ご意見3)産学連携諮問委員会運営の推移を見守りたいと思います。 以上の結果から過半数の賛同が得られましたことと、審議依頼の際に「尚、ご回答がない場合は賛成いただいたものとさせていただきます。」とさせていただいておりましたので、 以上 |
||
| 2022年6月8日 | ||
第1回産学連携諮問委員会議事録を掲載しました。 |
||
| 2022年6月8日 | ||
第1回産学連携諮問委員会 |
||
【日本脳科学関連学会連合 第1回産学連携諮問委員会 議事録】日時2022年5月6日(金)12:00-14:15 場所Web会議(Zoom会議) 参加者阿部 修、池田 昭夫、池田 和隆、大隅 典子(プレ会議2)、岡野 栄之、尾崎 紀夫、小澤 一史、加藤 忠史、川合 謙介(プレ会議2)、工藤 與亮、黒田 輝(プレ会議2)、後藤 純信、齊藤 延人、高橋 良輔(プレ会議1)、竹島 多賀夫(プレ会議1)、田中 謙二、林(高木) 朗子、平田 幸一(プレ会議2)、藤原 一男、松田 哲也、山脇 成人(プレ会議1)、石山 健夫、上野 太郎、小原 喜一、菊地 哲朗、北 陽一、白尾 智明、萩原 一平、菱田 寛之、平田 晋也、守口 善也 議事次第1.自己紹介 議事内容・池田委員(産学連携諮問委員会準備WG長)より産学連携諮問委員会の準備経緯等が説明された。 1.自己紹介 2.収録済み動画の視聴(高橋委員、竹島委員、川合委員、黒田委員、平田幸一委員、大隅委員) 3.委員長互選 4.委員会で情報共有しておくと良いことの情報提供 5.優先検討テーマについての議論 産学連携諮問委員会活動内容(案) 脳科連運営委員会の諮問を受けて、産学に跨る脳科学コミュニティの産学連携に関する事項の総意形成およびその政策提言に資する活動を行う。個別の産学連携事業の実施は、会員学会、連携法人会員、既存・新規の産学連携コンソーシアムなどで行われるよう、方向付けの役割を担う。具体的には以下の活動を行う。 <中核活動> <その他の活動(今後委員会で優先順位を検討)> 6.今後のスケジュール 以 上 |
||
| 2022年6月8日 | ||
メールマガジン5月号を掲載しました。 |
||
| 2022年5月19日 | ||
「産学連携諮問委員会」と「連携法人会員」について掲載しました。 |
||