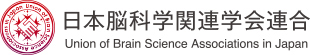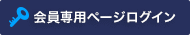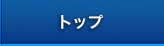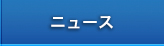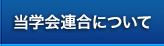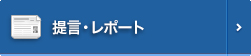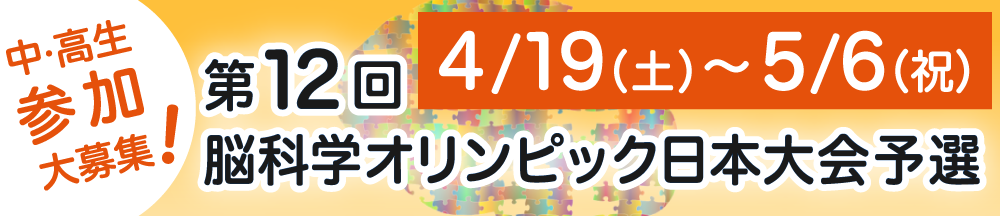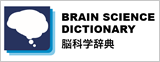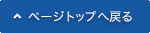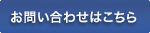ブログアーカイブ
| 2021年7月6日 | ||
第25回運営委員会議事録を掲載しました。 |
||
|
第25回運営委員会議事録を掲載しました。 |
||
| 2021年7月6日 | ||
第25回運営委員会 |
||
【日本脳科学関連学会連合 第25回運営委員会 議事録】日時2021年6月19日(土)11~12時 場所Web会議(Zoom) 参加者(敬称略) (オブザーバー参加) (欠席) 議事(1)事務局移転・委託について (2)会計監査委員について 以 上 |
||
| 2021年6月28日 | ||
会員学会年次大会情報を更新しました。 |
||
|
会員学会年次大会情報を更新しました。 |
||
| 2021年6月14日 | ||
第24回運営委員会議事録を掲載しました。 |
||
|
第24回運営委員会議事録を掲載しました。 |
||
| 2021年6月14日 | ||
第24回運営委員会 |
||
【日本脳科学関連学会連合 第24回運営委員会(拡大運営委員会) 議事録】日時2021年5月16日(日)15:00~17:20 場所Web会議(Zoom) 参加者(敬称略) (欠席) 事務局:理化学研究所 脳神経科学研究センター 吉川、孝子 開会挨拶伊佐代表より開会挨拶および理化学研究所・吉川センター長室長の紹介がなされた。 議事1. 事務局移転・委託について 2. 日本医学会連合との関係について 3. 脳科学オリンピックの運営について 4. 産学連携委員会の設置について 5. 運営規約について 6. 6月30日評議員会の議題について 7. 将来構想委員会の活動について 8. 日本学術会議の協力団体について 9. 脳科連ジャーナルについて 10. 脳科学エデュケーター制度について 11. コロナ禍でのメンタルヘルスについて 12. 広報に関連して 以上 |
||
| 2021年6月3日 | ||
『知ってなるほど!脳科学豆知識』第22回「磁気で脳の回路を調整する?」を掲載しました。 |
||
|
『知ってなるほど!脳科学豆知識』第22回「磁気で脳の回路を調整する?」を掲載しました。 |
||
| 2021年6月3日 | ||
特別寄稿 NPO法人「脳の世紀推進会議」の紹介と入会のお願い |
||
|
アドボカシーというカタカナ語はご存知でしょうか?アウトリーチというカタカナ語は公的研究費をもらう際に研究の意義を社会に周知するための講演会などを課される場合があり、良くご存知と思います。アウトリーチはこのように一般社会に向けて科学研究の意義や成果を知らせることを主な目的としています。例えば、日本学術振興会(JSPS)の科研費ハンドブックには「科研費は、国民から徴収された税金等でまかなわれるものであり、研究者は、その実績や成果を社会・国民にできるだけ分かりやすく説明することが求められています。」(同ハンドブック22頁)とあり、また日本学術振興会特別研究員にもアウトリーチ活動が奨励されています(日本学術振興会特別研究員遵守事項および諸手続きの手引3頁)。 ボトムアップとトップダウン研究費 トップダウン型研究テーマの設定は他の研究分野と競合 優れた若手の獲得も他の分野と競合 脳科学に特化したアドボカシー活動の重要性と「脳の世紀推進会議」の役割 「脳の世紀推進会議」への参加を 特定非営利活動法人(NPO)「脳の世紀推進会議」理事長 |
||
| 2021年6月1日 | ||
メールマガジン5月号を掲載しました。 |
||
|
メールマガジン5月号を掲載しました。 |
||
| 2021年5月12日 | ||
IBRO-APRC Webinar Horizonsのお知らせ |
||
|
国際脳研究機構アジアオセアニア地区委員会(IBRO-APRC)とアジアオセアニア神経科学連合(FAONS)は連携して、IBROの2nd Global Neuroscience Horizons Webinarを共催する運びとなりました。 今回のテーマは「 Translational neuroscience and novel therapeutics can yield new treatments for neurodegenerative diseases across the Asia/Pacific region 」で、日本からは柚崎通介先生(慶應大学)にご登壇いただきます。 日時は2021年5月31日(月)日本時間15時-18時半 Webpage 今後IBRO-APRCとFAONSでは、このようなアジア地域の研究者に向けたWebinarを定期的に行っていく予定です。 日本脳科学関連学会連合代表 ———————————————————- IBRO is excited to announce our 2nd Global Neuroscience Horizons Webinar on 31 May 2021 with Profs. Jafri Malin Abdullah, Cliff Abraham, Julie Bernhardt, Michisuke Yuzaki, Amy Fu, & Yong Shen. The webinar will focus on how translational neuroscience and novel therapeutics can yield new treatments for neurodegenerative diseases across the Asia/Pacific region and will be chaired by Prof. Pike See Cheah (chair, IBRO-APRC)& Dr. Lin Kooi Ong. Registration is free and open to all!
1.Webpage 2.Social media – On Twitter: https://twitter.com/ibroSecretariat/status/1390645881821618176?s=08 |
||
| 2021年4月28日 | ||
日本学術会議のより良い役割発揮に向けて |
||
|
2021年4月22日に、日本学術会議より「日本学術会議のより良い役割発揮に向けて 」 特に本連合とも関係致しますのは21-22ページにラインマークを引きました点、下記かと思います。 (1) 研究者コミュニティとの対話 (2) 国民との対話と科学の成果を還元する情報発信力強化・広報部署強化 (3) 科学的助言をめぐる関係者・関係機関との対話 |
||