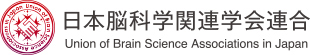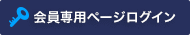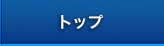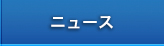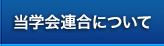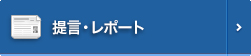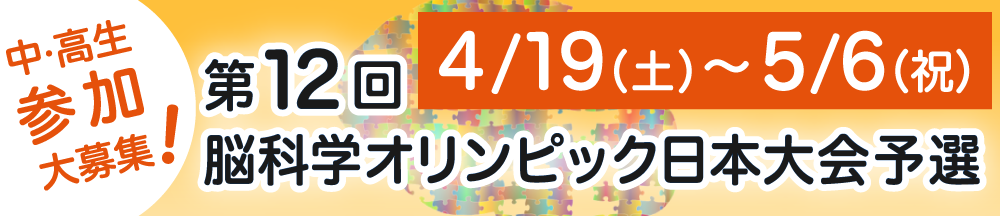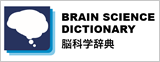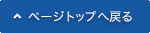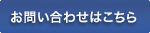ブログアーカイブ
| 2018年1月16日 | ||
第19回将来構想委員会議事録を掲載しました。 |
||
|
第19回将来構想委員会議事録を掲載しました。 |
||
| 2018年1月16日 | ||
2017年第3回(通算第19回)脳科学関連学会連合将来構想委員会 |
||
【議事録】日時2017年7月11日(火曜日) 場所ネット会議 出席者今水寛(日本心理学会)、岡本仁(理化学研究所脳科学総合研究センター)、 欠席者伊佐正(日本生理学会)、大隅典子(新学術領域・次世代脳)、 議事1.趣旨説明・柚崎委員長より脳科学委員会作業部会で討議が続けられてきた「神経回路レベルでのヒトの脳の動作原理の解明」中間取りまとめについて、脳科学コミュニティとしての意見を取りまとめたい旨が説明された。 2.「神経回路レベルでのヒトの脳の動作原理の解明」中間取りまとめ(案)・7月14日に行われた脳科学委員会作業部会で報告された中間取りまとめについて、作業部会の委員でもある花川委員より説明された。 3.自由討議(岡本)非ヒト霊長類とヒト脳の主観比較によってどのように目的とする「回路レベルでの動作原理の解明」に至ることができるのかがよく理解出来ない。齧歯類などのモデル動物はあくまで神経回路を計測・制御する技術開発のために用いると書かれているが、むしろ齧歯類などのモデル動物によって回路レベルでの動作原理を解明し、その結果を非ヒト霊長類やヒト脳に演繹するのが世界の脳科学研究の趨勢であると思う。またAIをどのように脳科学に用いるかという記述が多いが、脳科学からAIという流れについても書き込むべき。 (鍋倉)提⽰されているポンチ絵では、ヒトと⾮ヒト霊⻑類との⽐較や、病態の解明が項⽬として出ているが、ヒト⾃体の脳機能解明、特に正常脳の機能解明をもう少し全⾯に出すことが重要ではないか。実際に日本の強みの一つは、7T MRIを中⼼に3D SEM、⽣体顕微鏡イメージングなどのシームレスイメージングがある。 (尾崎)前回の伊勢志摩サミットでは認知症を中心とした国際連携が提言されていたが、次回のカナダサミットではこれを他の精神疾患や発達障害に拡張される動きがあることも留意しておく必要がある。中間取りまとめでは、強みを活かすことも加えて、日本が弱いところ、例えばブレインバンク(死後脳)やImaging Geneticsなども伸ばして国際連携に繋げることを書き込む必要がある。AIについては厚労省でも大幅に取り入れようとする動きがあるのでうまく連携するべきである。 (尾藤)全体として総花的であり、どのような時間軸で日本の強いところを更にバックアップして弱いところを持ち上げるのかがわかりにくい。「AIと脳科学をつなぐ人材の育成と確保」にしても、国内での待遇など環境を整備しないと育てたAI分野の人材はどんどん海外に流れてしまう。 (山森)「異種間比較」についての議論が出たが、これは革新脳プロジェクトでマーモセット脳とヒト脳間で実際にプロジェクトが動きつつあり十分実現可能である。またヒト脳の動作原理は、確かに齧歯類や非ヒト霊長類とヒトの比較は簡単ではないが行動課題を工夫することで可能と考える。 (川人)AI研究と脳科学については前回の脳科学委員会でお話しさせていただいた。AI研究はなんと言っても注目されている分野であり予算の獲得はしやすい。また岡本委員からご指摘があった、脳科学からAI研究に向かう流れであるが、これは中間取りまとめに含まれている。アメリカではHuman Connectomics Projectでは正常脳の解析は確かに進んでいるものの、これはあくまで一カ所の施設で健常者を集めて行われた研究であり、これを精神疾患患者に適用するは難しい。日本では非常に多くのMRIが導入されており、機種の違い撮像条件の違いを標準化することができればこれは強みに活かしていくことができる。 (今水)心理学分野からの貢献としてはヒトと非ヒト霊長類の種間比較のための心理学実験や行動実験という面から貢献できると考える。心理学分野からの学際的人材育成についてももっと工夫できると思う。 (望月)ブレインバンクでは施設面だけでなく、神経病理医が不足していることが深刻な問題となっている。また、死後脳の国際化については法律的に慎重に行う必要がある。 最後に脳科学委員会の作業部会のミッション、さらに脳科学委員会、脳科学関連学会連合の将来構想委員会、学術会議の連動について意見が交換された。 以上の討議を踏まえて、柚崎委員長から以下の2点が提案され閉会となった。 以上 |
||
| 2017年12月4日 | ||
『知ってなるほど!脳科学豆知識』第7回「脳はプラスチック!? 〜記憶は伸びたり縮んだり〜」を掲載しました。 |
||
|
『知ってなるほど!脳科学豆知識』第7回「脳はプラスチック!? 〜記憶は伸びたり縮んだり〜」を掲載しました。 |
||
| 2017年9月11日 | ||
『知ってなるほど!脳科学豆知識』第6回「赤ちゃんの言葉の発達とともに変わる親の脳活動」を掲載しました。 |
||
|
『知ってなるほど!脳科学豆知識』第6回「赤ちゃんの言葉の発達とともに変わる親の脳活動」を掲載しました。 |
||
| 2017年7月28日 | ||
「精神・神経疾患の治療法開発のための産学官連携のあり方に関する提言」を掲載しました。 |
||
|
「精神・神経疾患の治療法開発のための産学官連携のあり方に関する提言」を掲載しました。 |
||
| 2017年7月24日 | ||
第8回評議員会、第16回運営委員会議事録を掲載しました。 |
||
|
第8回評議員会、第16回運営委員会議事録を掲載しました。 |
||
| 2017年7月24日 | ||
第16回運営委員会 |
||
【日本脳科学関連学会連合 第16回運営委員会 議事録】日時2017年6月28日(水曜日) 15:15~15:30(※評議委員会に引き続き実施) 場所理化学研究所 東京連絡事務所 参加者(敬称略) 議事(1)新規学会加入審査に係る覚書案について ・当該学会の財務体質や法人格等の客観的な基本情報の提出を求める これを踏まえ、覚書案及び以下の要素を盛り込んだ入会申込書の雛形案を事務局において作成、運営委員が確認することとした。 ・会則の有無 ・法人格の種別 (2)脳科学リテラシー委員会について(高等教育における教科書および指導要領改善について) ・現実的には教科書に手を入れることは大きな労力がかかり難しい。副教材を作成するか、スーパーサイエンスハイスクール(SSH)等へ働きかけをしていくことが効果的ではないか。 本件については引き続き対応を運営委員会で検討することとした。また、事務局より本委員会の位置づけについて確認があり、岡部代表より、現時点では将来構想委員会や広報委員会の様な規約に定められた委員会とは位置付けず、アドホックな委員会として扱うこととしたい旨提案があり、了承された。 以 上 |
||
| 2017年7月24日 | ||
第8回評議員会 |
||
【脳科学関連学会連合 第8回評議員会 議事要録】日時2017年6月28日(水曜日)13:00~15:05 場所理化学研究所 東京連絡事務所 出席者(名簿順、敬称略) 欠席者(名簿順、敬称略) 事務局:姜、立花、小野田、柴田 配布資料資料1-1 第5回評議員会議事要録 議事1.開会 2.出欠確認 3.連合代表からの活動報告 ・第5回~第7回評議員会議事要録、第14回、第15回運営委員会議事要録の確認 この中で、第15回運営委員会において、脳科学オリンピックへの対応および脳科学に関する正確な知識を若い世代に伝えていくことを主目的とする「脳科学リテラシー委員会」の設置が承認された旨補足があった。 4.脳科学将来構想委員会の活動報告 ・第14回~第18回将来構想委員会の確認および当該委員会の活動報告 この中で、脳科学総合研究センターへの期待を連合としてとりまとめ理研経営陣に手交したことに対し、理研BSI所蔵の加藤評議委員より尽力に感謝する旨の発言があった。 5.議決事項 2. 次回以降の新規学会加入時の審査について、今後、運営規約定める4条件の他、当該学会の独自性、国際性、脳科学周辺領域への影響等についての運営委員会委員の意見を元に評議員会の採決によって可否を判断すること明記した覚書案について大筋で承認した。ただし詳細な文言および要件について挙がった以下の意見を踏まえ、運営委員会に修正案の検討を一任した。 ・当面はよいとしても、規模感の想定があるべき。規模に比例して事務負担も増える。 (2)広報委員の選出 (3)会計監査委員の選出 (4)2016年度決算および監査について (5)2017年度予算案について 6.報告事項 (2)脳科連提言「理化学研究所における脳科学への期待」について (3)日本学術会議「マスタープラン2017」および文部科学省研究振興局学術機関課によるロードマップ2017の策定について (4)日本学術会議提言案「脳科学における国際連携体制の構築」について (5)日本学術会議提言案「精神・神経疾患の治療法開発における産官学連携のあり方に関する提言」について この中で、(5)については、企業が参画しないと動かない取り組みであり、製薬業界の業界団体である製薬協に協力を依頼していること、今後も必要に応じ説明に行くこと等補足説明があった。また、(3)~(5)に共通して、学術会議の提言は「出しっ放し」で終わり予算措置やその後の取組につながっていないという批判があり、特に企業を巻き込んだ取組みである場合は信用にもかかわる問題なので、その後の取組をきちんとフォローアップしていくことが重要だという指摘があった。 (6)高校の教科書における脳科学の取扱いについて(※評議委員会冒頭に実施) (7)広報委員会からの活動報告について ・パンフレットの改訂 この中で、脳科学豆知識については平易で理解しやすいものにまとまっているので各方面からアクセスしやすくなるような工夫してはどうかと提言があった。 7.連絡事項 ・2017年の会費納入について 以 上 |
||