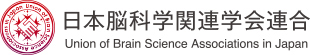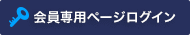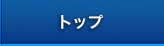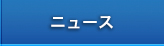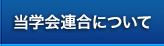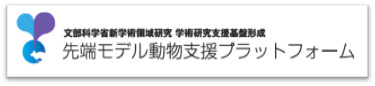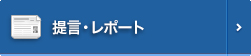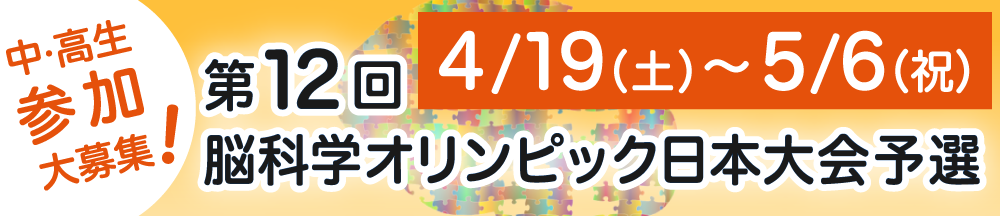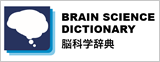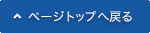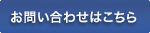ブログアーカイブ
| 2017年7月10日 | ||
会員学会年次大会情報を更新しました。 |
||
|
会員学会年次大会情報を更新しました。 |
||
| 2017年7月10日 | ||
第14-18回将来構想委員会議事録を掲載しました。 |
||
|
第14-18回将来構想委員会議事録を掲載しました。 |
||
| 2017年7月10日 | ||
第15回運営委員会議事録を掲載しました。 |
||
|
第15回運営委員会議事録を掲載しました。 |
||
| 2017年7月10日 | ||
2017年第2回(通算第18回)脳科学関連学会連合将来構想委員会 |
||
【議事録】日時2017年5月19日(金曜日) 場所ネット会議 出席者伊佐正(日本生理学会)、川人光男(日本神経回路学会)、 議事1.前回議事録確認2.脳科学委員会作業部会での答申についての学会連合としての意見表明 前回討議の内容に加えて、「国際連携データプラットフォーム」の形成を促進する前段階として、国内におけるヒト・動物をつなぐゲノム・画像データベースの整備が必須であることが尾崎委員から強調された。これには研究倫理(個人情報法)の問題も絡んでいることが花川委員より指摘された。関連した問題として、脳の動作原理の解明を進めるという大目標が掲げられている一方で、資料5-3では分子レベルでの理解について触れられていない点について柚﨑委員より指摘があった。これらの意見は脳科学委員会作業部会にfeedbackすることで合意した。 3.「長期的展望に立つ脳科学研究の基本的構想」の今後の進め方 最初に川人委員より平成21年の一次答申提出時の背景と体制について説明があり、引き続いて自由討論となった。
以上 |
||
| 2017年7月10日 | ||
2017年第1回(通算第17回)脳科学関連学会連合将来構想委員会 |
||
【議事録】日時2017年5月16日(火曜日) 場所ネット会議 出席者平井宏和(日本神経科学学会)、伊佐正(日本生理学会)、 議事1.趣旨説明・柚﨑委員長より、以下の通り趣旨説明を行った。
2.脳科学委員会作業部会答申(上記1))についての説明(加藤、伊佐)・加藤、伊佐委員より、第37回脳科学委員会で提出された「国際連携を見据えた戦略邸脳科学研究の推進方策について」(資料5-2)と、これに基づいた「神経回路レベルでのヒトの脳の動作原理の解明」(資料5-3)について説明を行った。 3.自由討議(岡本)動作原理の解明とあるが、資料5-3を見る限りモデル動物について例えば齧歯類や魚類の重要性や役割が書かれていないのではないか。 (望月)バイオリソースとしてのBrain Bankについても資料5-3に明確に書き込んで欲しい。 (今泉)13ページにて「心理系研究者の参入・連携が不足」が日本の弱みとして書かれている点についてもう少し説明して欲しい。 (鍋倉)アメリカやヨーロッパのプロジェクトとの整合性や棲み分けをどう考えるか整理する必要がある。国際連携については「日米脳」の枠組みもある。 (平井)中国・インド・カナダなどとの国際連携は考えなくてよいのか。 (尾藤)日本が海外発の国際連携プロジェクトに参加できるような枠組みが欲しい。 (川人)どういう国際連携をすればどういうメリットがあるか整理が必要。 (山森)国際連携の枠組みとしてFellowshipを加えても良いのでは。 以上 |
||
| 2017年7月10日 | ||
2016年第4回(通算第16回)脳科学関連学会連合将来構想委員会 |
||
【議事録】日時2016年10月23日(月曜日) 16:00-18:30 場所東京大学 医学部教育研究棟 2階第1セミナー室 出席者岡部繁男(日本解剖学会)、高橋良輔(日本神経学会)、 欠席者伊佐正(日本生理学会)、川人光男(日本神経回路学会)、 議事1.開会にあたって・岡部代表より、日本脳科学関連学会連合の設立経緯と、連合内における将来構想委員会の位置づけ、1~3号委員の選出経緯、およびこれまでの将来構想委員会の活動が報告された。 2.各委員の紹介・代表・副代表を含め、将来構想委員全員による自己紹介を行った。 3.委員長の選定・事務局より、委員長の選出基準、および選出された委員長より副委員長2名を後日指名することが確認された。 ・事前投票及び当日投票の結果、1回目の投票で過半数を得た柚崎通介委員が将来構想委員長に選出された。 4.今後の進め方・20周年を契機として理化学研究所脳科学総合研究センター(理研BSI)に対して組織見直しの対象となっていることを踏まえ、前期の将来構想委員会からの引き継ぎ課題として、脳科学コミュニティとしての今後の対応について討議された。 ・まず岡部代表および岡本委員より、2016年10月以前に行われた脳科学委員会等での理研BSIによるプレゼンや、それに対する委員の評価などが説明された。 ・討議の結果、将来構想委員会を中心として理研BSIへのこれまでの活動への評価と今後への期待について、脳科学コミュニティとしての意思表示を示しておく必要性があるとの意見で一致した。 ・柚崎委員長が文書のとりまとめ役として、将来構想委員会にてたたき台の作成と各委員からの意見の反映を行い、最終合意文書の作成を目指すことで合意した。とりまとめ文書は加盟23学会の評議員に諮り、合議の上で全23学会のクレジットが入る形で、脳科学コミュニティを代表した意見として表明することとなった。 以上 |
||
| 2017年7月10日 | ||
2016年第3回(通算第15回)脳科学関連学会連合将来構想委員会 |
||
【議事録】日時2016年7月11日(月曜日) 10:00-12:30 場所東京大学 医学部教育研究棟 2階第3セミナー室 出席者岡部繁男(日本解剖学会)、松田哲也(玉川大学脳科学研究所)、 欠席者高橋良輔(日本神経学会、新学術領域研究)、木山博資(日本神経化学会)、 議事(伊佐)今後のタイムスケジュール ●考え方の基本的な意見(伊佐)他との連携をうまく保ちながら取り込まれないようにしつつ、理研の中枢部とBSI(脳科学コミュニティ)の双方が満足できる提案を出す必要がある。また社会的に見ても脳科学が今後も重要だ、と理解していただけるような方向へ持っていくのがよい。 (伊佐)BSIのこれまでのあり方(ここが足りてなかった等)を踏まえてバージョンアップできるような論理構築をしていきたい。 (伊佐)「大学でも他の研究機関でもやっているではないか、その上で何故脳センターが必要なのか」というロジックスを再構築する必要がある。 (鍋倉)圧倒的にBSIにしかできないこと、を前面に出す必要がある。戦略をたてるにあたって、大学ではできない、BSIにしかできないことは何なのか、というふうに考えていく必要がある。 (鍋倉)例えば高次のMRIをつくるといった技術的なものをつくる、理論をつくる、など、何か他ではできない切り口が必要。そういう融合のためには予算を投じてもいい、価値がある、という方向にもっていってはどうか。 ●BSIのこれまでと現状の資料について(柚崎)理研のトータル額は一緒なので、脳研究に費やしている研究費は他と比べてどうなのか、なぜ脳研究に費やす必要があるのか、で説得していかなければならない。 (岡部)理研の生物系センターの中でみるBSIの予算比率、科研費の獲得状況はどうか。 (柚崎)交付金と比べて科研費の割合はどうか、という資料を示すとよいのではないか。 ●今後のBSIのあり方についての意見(柚崎)「統合」をキーワードにして臨床との統合、周辺科学との統合としてはどうか。 (松田)革新脳のような国としてやらなければならないトップダウンのビッグプロジェクトを引き受けてBSIで研究するとか。理研でしかできないような技術開発を行ってそれをコミュニティに配ることによって日本の脳研究レベルを上げる、という役割をするなど。 (柚崎)研究の最先端を追及してそれを周辺大学や研究者とシェアして融合する、という意味であればよい。例えばBSIで融合チームをつくり、そこに大学も入れて、というかたちならわかる。 (松田)特定になったときに「ハブ」を全面的に出すというのは1つの方法かと思う。例えば技術開発でテーマを設定しそれごとのハブ機能(知の結集)をつくり、それに対して必要な人を呼んできて開発力を高める、そこでできた技術を脳コミュニティに返していく、かたちをつくるというのは効果的である。 (伊佐)トップダウンの大目標があってそれに対して理研はどういったプロジェクトをやるのか、そのイニシアチブをとり、足りない部分は大学と連携する、というのが有効な方法だと思う。 (岡部)理研の将来戦略として、ヒトと動物を理論でつなぐような戦略研究、融合的な分野に対する戦略的な投資、革新脳で実績が出つつあるようなデータベースを介したコミュニティのハブ的な役割、を柱にしてはどうか。研究内容ではなくハブの種、戦略的な枠組みの提案をしてほしい。 以上 |
||
| 2017年7月10日 | ||
2016年第2回(通算第14回)脳科学関連学会連合将来構想委員会 |
||
【議事録】日時2016年5月25日(水曜日) 10:00-11:00 場所ネット会議 出席者伊佐先生、山森先生、池谷先生、岡本先生、松田先生、岡部先生、鍋倉先生、 傍聴横田室長、姜室長代理、星屋副主幹、柴田、道本、金居 議事1. 脳の情報処理の理解とその応用による社会貢献○伊佐先生より経緯、改定案についての説明 2-1-1 認知症、うつ病に代表される精神・神経疾患の克服に向けた取り組み→「融合脳」 2-1-3 脳の情報処理の理解とその応用に向けた取組
(松田)現在、国際連携をキーワードとして今年度の調整費を行っており、数週間以内に決定する見込みで、このようなプロジェクトが採択される可能性がある。今回は設計図を作ってゴールを見据えた基礎研究を行うということを示す必要がある。ここでの意見を踏まえて修正した後の脳科学委員会でのプレゼンを文科省が参考にし、プロジェクト案を作成していく。調整費の枠と来年度の概算要求に向けてのプロジェクトの提案という2つある。現在は潤沢に予算がとれるわけではなく、一つのプロジェクト10億円以下で考えなければならない。記憶と意思決定を2つ同時に出すと、2つを同時にすることはできない。まずはどの部分から行うか優先順位を考えてプレゼンしたほうがよい。 (伊佐)調整費については早い段階からAMEDより相談を受けていた。調整費は単年度。6月、7月に公募し、平成28年度調整費をつける。平成29年度以降はそれを膨らませて10億円くらい。 (松田)しない。 (伊佐)このプロジェクトの概要について戦略的側面からどういう順序で考えていくか合意・コンセンサスを得たい。 (岡本)計画はよいが、1の記憶は理研からの提案とおっしゃったが、理研が提案したものはもっと包括的なプランで、記憶だけではない。記憶と意思決定は区別しにくく、重複している。話を進めていく過程で変な切り分けが行われないようにすべき。 (岡部)調整費で計画の一部が実現するかもしれないが、調整費は単年度で、そのあとどうつなげていくかが重要。次回の脳科学委員会では広めのスタンスで話してもらったほうが自由度が残る。脳科学委員会で安西先生から、説明の中で使われている用語に定義の不明瞭なものが多く、整理をしたほうがいい、という意見があった。神経科学の研究者は理解できてもほかの分野の人から見ると適切ではない印象を与えることがあり、次回は慎重にしていただいたほうがいい。 (伊佐)「ゆらぎ」が別のものを想像させることや、ストレスは外的なものだという方もいる。言葉の問題はサイエンスの発展に応じて変わっていくと思う。脳科学委員会は外部の分野の方も多いのでそのあたりが難しい。 (岡本)階層並列的という用語の意図は?脳は並列処理もある。 (伊佐)あいまいなところがあったかもしれない。 (池谷)【音声不明瞭】 (川人)すすめていただいている案でよいと思う。人工知能では経産省、文科省、総務省、理研のAIP、クレスト公募始まった。融合脳の研究者の話で、審査委員会では何も言われないのに、計画を出す段階で官僚レベルが出てくると嘆いていた。 (鍋倉)岡部先生の意見に賛成。調整費で方向性を出し、次の概算要求でライフ課、AMEDとして、向こうが作りやすい形で残しておく。調整費がつかなかった場合も考えておく。 (望月)人工知能は全く入らないのか。 (伊佐)人工知能という言葉を入れるのは賢明でないと思うが、個人的な意見では数理モデルを作るということは残し、モデル分野で手法として人工知能を使うことはあるのではないかと思う。 (望月)調整費、概算要求もいいバランスで載せてほしい。両方とも確定していないということで難しいかなと思う。 (山森)ストレスが外的なものだという考えは違う。例えば最近内閣府が発表した自殺については、病気が理由となっているものが7割。身体的病気、精神的病気という理由が半々ずつ。伊佐先生が言ったように新しい概念を少しアウトサイド周辺の領域含めて理解していただくように説明するというのは大事だと思う。 (伊佐)まとめると、振興調整費の部分は6,7月公募2億円くらい。その後、文科省とAMEDはそれを膨らませて10億円くらいの概算要求をしたいと考えている。2億円の振興調整費の部分をどこからスタートすべきか。入口に近いところと出口に近いところ。将来的な予算の獲得を考えると全部ここに含めてしまうと取りにくい。個々の研究者が両方に出せるが、外から見たときにプロジェクトの目標が違っているように見えることが必要。入口から出口まで含めて概算要求に持っていくのか、出口よりのところにプロジェクトをつくっていくべきか。振興調整費で最初2億をつけるとしたらどこから始めるか、それ以外のテーマとして、3つ4つくらいほしい。我々が言えるのはそのくらいではないか。 (池谷)【不明瞭】 (岡本)意思決定はよいと思うが、実際には海馬・偏桃体の相互作用によって意思決定が行われるので、絵を書くときは、もう少し脳の広い部分を入れておいたほうがいいと思う。 (伊佐)入力側も組み込むということで。今回は出口に重きを置いたところで振興調整費を取りに行くというところで合意していただければ。 (岡部)逆の意見で、回路の絵をあまり強調しないほうが良いと考える。内的環境、外的環境をもっと書き込んで、単に回路研究でないという絵にしてほしい。 (伊佐)そういう図にしたい。 (岡本)意思決定、行動選択を扱う際に、ニューロエコノミーなど脳科学を踏まえたうえで人の高次機能を研究するという部分もある。これは回路的に書いてあるので、そういうイメージがこの研究計画から浮いてこない。 (伊佐)動物実験が中心的に考えたスキームになっているので、もう少し臨床でないヒトのMRI研究が入りやすくするというのは重要なポイント。 (??)タイトルを見ると出口は社会貢献。社会貢献がどうなのか、脳科学委員会としては把握しにくいのではないか。 (伊佐)自殺の予防やギャンブル、依存症等まとまって書いていないところもあるので、修正したい。振興調整費で限定的な枠からまず出して、概算要求がそれを基盤にしていろんなポイントまでを加えていくべきだと思う。個人的意見だが、振興調整費では基本的な基礎研究を1年前から始め、次に破たんのメカニズムなど、より広く、動物と人を比較し、モデル化して、後から概算要求として付け加えることができればよいと思う。 (鍋倉)科研費改革で、心理と脳科学は現段階では難しいということで、認知と脳科学はコミュニティとしては難しい。今回の意思決定がひとつの突破口になるのではないか。そういう意味では、出口の意思決定は見せる必要があるが、あまりにも回路に偏らない。最終的にストレス、対人となると心理系の人たちとのコミュニケーションが非常に重要になると思う。あくまでもAMEDなので基礎研究と言いながら出口がかなり重要視されると思う。見せ方としては単に記憶というよりは意思決定をみせるのであれば、心理の安西さんなどを説得するような見せ方が必要である。 (伊佐)人の研究も時間がかかるので高次的なところを中心に最初見せて心理の人も加われるという大枠の枠組みを作り、2年目以降は緻密な回路の解析、破たん、病気のメカニズムにつながる研究、モデルなど。1年目には人の研究を入れるように考える。 (岡部)学会連合からの発表なので、1年目、2年目はライフ課やAMEDが考えることである。我々は、このような研究計画を行うのであれば戦略としてどのような研究を先行し、どのような形で広げることが最終的なゴールに最もスムーズにたどり着けるのか、ということだけを言えばいい。 (伊佐)心理学会からの将来構想委員会委員がいないのは問題かもしれないと思った。岡部先生が言った内容を脳科連からとして提案をする。 (岡本)AMEDのサポートのGやバイオリソース、両方とも実用的な出口には関係ないプロジェクトである。出口にかかわっていなければAMEDがサポートしないということはない。 (伊佐)入口がすべて人だけではなく、人も含めて意思決定のメカニズムを行うというもの。 以上 |
||
| 2017年7月10日 | ||
第15回運営委員会 |
||
【日本脳科学関連学会連合 第15回運営委員会 議事録】日時2017年2月10日(金曜日) 場所メール審議 参加者(敬称略) 議事(1)脳科学リテラシー委員会について (2)高校の教科書における脳科学の取扱いについて 審議の結果議題(1)(2)ともに運営委員の承認を得た。 以 上 |
||
| 2017年7月7日 | ||
「若手支援技術講習会 2017」参加者募集のご案内 |
||
|
研究をスタートさせたばかりの大学院生から、博士研究員および助教等の若手研究者のみなさまを対象に、『全員参加型の講習会』を、文部科学省新学術領域研究(学術研究支援基盤形成)先端モデル動物支援プラットフォームの主催で開催いたします。 参加対象者は、平成29年度科学研究費を獲得している研究代表者の研究グループに所属する若手研究者(概ね20~30代)です。代表者本人の参加も歓迎します。 会期:2017年9月7日(木)〜9日(土)の3日間 詳細、参加申込みは先端モデル動物支援プラットフォームホームページをご覧ください。 お問合せ 多彩な研究領域の技術や知識を習得して見聞を広めること、また同世代の研究者によるネットワークを構築する絶好の機会でありますので、奮ってご参加ください! |
||