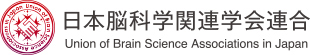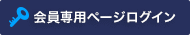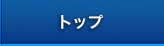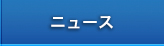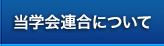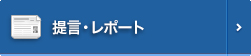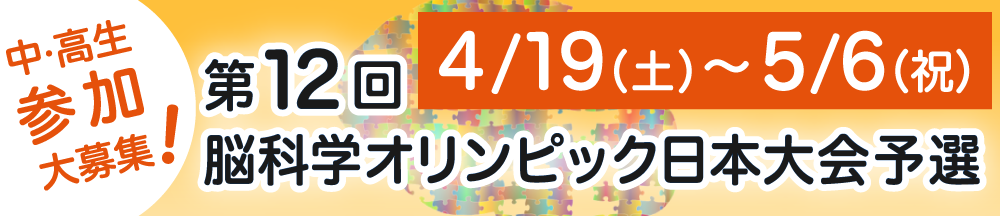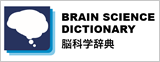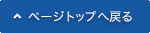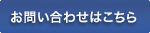ブログアーカイブ
| 2013年3月8日 | ||
第2回~4回脳科学将来構想委員会議事録を掲載しました。 |
||
| 2013年2月7日 | ||
第5回脳科学将来構想委員会 |
||
【脳科学関連学会連合 第5回脳科学将来構想委員会 議事録】日時2013年2月7日(月曜日)16:00~17:30 場所オンライン会議 出席者(名簿順、敬称略) 議事1.トップダウン型研究 新規プロジェクトの提案について 委員より以下の意見交換があった。
運営委員からのコメント等を踏まえて今後本文の修正を行うこととなった。追加のポンチ絵については、事務局に作成を依頼することとなった。 2.日本学術会議次期(22期)マスタープランについて 以上の報告を受けて、委員より以下の情報提供、意見交換があった。
以上の議論を経て、INCFでの国際共同研究については理研BSIの担当者から、Allen研究所については同じく理研の田中啓治氏から情報を得ることとなった。また運営委員からの指摘として、研究項目(6)の「脳・こころ・社会」を一体化した研究の実現に向けた、異分野連携の推進、という部分については、「他の部分の記述とのつながりが薄く、そこだけが「脳科学として一体となって取り組む」というように読めない」という指摘に対応するため、修正することとなった。 続いて委員より、具体的な申請の際に必要となる書式について説明があり、現在抜けている項目として、「経費」「年次計画」「実施機関」の三つについても議論する必要があるとの指摘がされた。これを受けて委員長より、実施機関の最終決定は運営委員会での議論が必要であること、将来計画委員会としては、提案された計画を実施する上で必須となるのがどの研究機関であるのか、というコメントは運営委員会に対して提出すべきであること、が提案され、了承された。経費と年次計画については今後検討することとした。 3.コミュニティへの周知・議論 続いて学術会議脳関連3分科会によるシンポジウムについての意見交換が行われ、シンポジウム構成としては、脳科学以外の分野の傑出した科学者に脳科学に期待するものを語っていただくセッション、脳科学内部からの情報発信、これらを受けてのパネルディスカッション、という3部構成とすることとなった。これを念頭において、適任と思われる講演者を3名、それぞれの委員が推薦することとなった。 4.今後の進め方について 以上 |
||
| 2012年12月27日 | ||
第2回~4回運営委員会議事録を掲載しました。 |
||
| 2012年12月27日 | ||
第4回運営委員会(メール会議) |
||
【日本脳科学関連学会連合 第4回運営委員会 議事録】日時2012年10月29日(月曜日)(メール配信日)~11月2日(金曜日)(回答締切日) 参加者日本生理学会:伊佐正 議題(1)学会連合HPの確認について(審議事項) 審議の結果議題(1)~(3)について全委員から承認を得た。なお、(2)会計監査委員については、投票の結果、岡部繁男 評議員(日本解剖学会)、黒澤美枝子 評議員(日本自律神経学会)に決定したことが報告された。 以上 |
||
| 2012年12月27日 | ||
第3回運営委員会(メール会議) |
||
【日本脳科学関連学会連合 第3回運営委員会 議事録】日時2012年9月14日(金曜日)(メール配信日)~9月25日(火曜日)(回答締切日) 参加者日本生理学会:伊佐正 議題(1)会計監査委員の選出について(審議事項) 審議の結果9月25日までに全ての委員から回答が寄せられ、議題(1)~(5)について全委員から承認を得た。なお、(1)会計監査委員の選出については全委員の賛同を得て以下の手順とすることが決定した。 以 上 |
||
| 2012年12月27日 | ||
第2回運営委員会(メール会議) |
||
【日本脳科学関連学会連合 第2回運営委員会 議事録】日時2012年7月31日(火曜日)(メール配信日)~8月7日(火曜日)(回答締切日) 参加者(名簿順、敬称略) 議題(1)平成24年度予算案について(審議事項) 審議の結果8月7日までに全ての委員から回答が寄せられ、議題(1)~(5)で提案された内容について全委員から承認を得た。 以 上 |
||
| 2012年12月25日 | ||
第4回脳科学将来構想委員会 |
||
【脳科学関連学会連合 第4回脳科学将来構想委員会 議事録】日時2012年12月25日(月曜日)15:00~16:30 場所オンライン会議 出席者(名簿順、敬称略) 議事1.トップダウン型研究 新規プロジェクトの提案について 以下の意見交換があった。
以上の議論を経て、今回の文案のタイトルを「心の階層的な機能指標の研究開発」とし、全身性疾患との関連性についての文言を「背景」「必要性」「具体的な研究内容」の項目に付け加えて将来構想委員会としての最終案とすることが承認された。 以上の報告を受けて、以下の情報提供、意見交換があった。
3分科会合同のシンポジウムの企画については本委員会もアイディアを出して学術会議分科会との共催とすることが認められた。シンポジウムのテーマは基礎と臨床脳科学の融合を目指すものとし、脳科学の重要性を他の研究分野に対してアピールするものを目指す。 6項目の研究計画について、それぞれの担当委員を決定した。(○印は責任者) それぞれの項目について、具体的な内容がわかる研究計画案(最終的には各項目数行に圧縮する予定だが、現時点では長めの文案で構わない)を作成し一月中旬までに提出する。1月8日の学術会議の分科会にて提案のフォーマットがわかるので、その内容については担当委員より情報提供をいただく。 続いて委員長より、現在提案されている複数のタイトル案を元にして、タイトルを決定したいとの提言があり、委員により議論が行われた。最終的に 以上 |
||
| 2012年11月19日 | ||
第3回脳科学将来構想委員会 |
||
【脳科学関連学会連合 第3回脳科学将来構想委員会 議事録】日時2012年11月19日(月曜日)15:00~16:20 場所オンライン会議 出席者(名簿順、敬称略) 議事1.トップダウン型研究 新規プロジェクトの提案について 以下の意見交換があった。
以上の議論を経て、今回の文案をさらに整理して学会連合への将来構想委員会からの提案とすることが承認された。
今後のマスタープラン案の作成スケジュールについて 以 上 |
||
| 2012年11月7日 | ||
第1回脳科学将来構想委員会議事録を掲載しました。 |
||
| 2012年11月7日 | ||
第1回運営委員会議事録を掲載しました。 |
||
|
第1回運営委員会議事録を掲載しました。 |
||