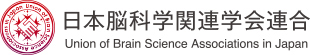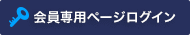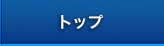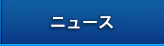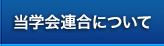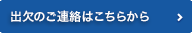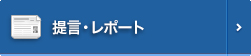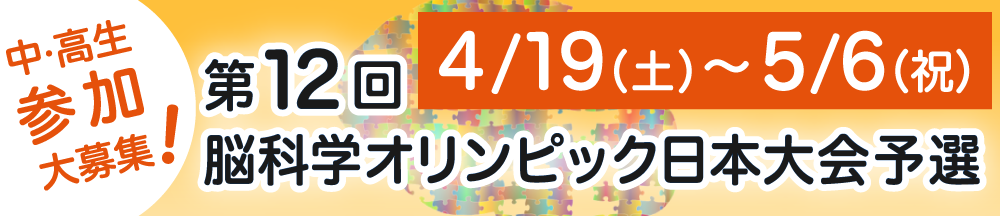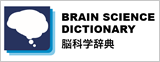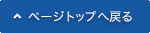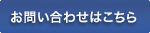ブログアーカイブ
| 2019年6月4日 | ||
第12回評議員会、第20回脳科学将来構想委員会議事録を掲載しました。 |
||
| 2019年6月4日 | ||
2018年第1回(通算第20回)脳科学将来構想委員会 |
||
【議事録】日時平成30年11月16日(金)16:00-18:00 場所東大医学部教育研究棟第7セミナー室(1304B) 出席者伊佐 正(日本神経科学学会)、礒村 宜和(日本生理学会)、田中 沙織(日本神経回路学会)、西田 眞也(日本心理学会)、笠井 清登(日本精神神経学会)、尾崎 紀夫(日本生物学的精神医学会)、池田 和隆(日本神経精神薬理学会)、尾藤晴彦(日本神経化学会)、定藤 規弘(自然科学研究機構)、花川隆(国立精神・神経医療研究センター)、岡本 仁(理化学研究所脳神経科学研究センター)、柚﨑通介(脳科学研究戦略推進プログラム)、大塚 稔久(革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト)、和氣弘明(CREST)、林(高木) 朗子(新学術領域・次世代脳)(敬称略) 欠席者望月 秀樹(日本神経学会)、勝野 雅央(日本認知症学会)、阿部 修(日本磁気 議事1.脳科学将来構想委員会委員の互選により、尾藤委員が委員長に就任した。 2.委員長提案に基づき、WG1「2020年マスタープランへの対応」、WG2「ゲノム医学への推進に必要な疾患ゲノム」、WG3「臨床データべースとAIを用いた解析」、WG4「20年後、50年後の脳科学ビジョンの策定」の4つのWGを設け、集中的に議論を進めていくことが了承された。 3.委員は各WGに分かれ、2年任期期間中における目標設定と推進計画について検討した。特に、WG1とWG2については、公募日程や各種メディカルゲノム構想との連携の可能性を考慮し、迅速に対応していくことが了承された。一方、WG3とWG4については、中長期ビジョンをとりまとめ、発信可能な提言の策定を目標とすることが合意された。 脳科学将来構想委員会WG1-4での議論についての報告WG1: マスタープラン2020への対応 (WG長:定藤 規弘(自然科学研究機構)) 上記議論に基づき改訂が進められ、将来構想委員会ならびに運営委員会での議論を経て、生理学研究所 定藤規弘を提案者とする改訂案が提出された。 ゲノム医学の振興に伴い、脳科学・精神神経医学領域におけるゲノム情報を取り扱うプロトコールの樹立と全国の研究・診療機関への周知にAll Japanで取り組む必要性が高まっている。他疾患群においては、例えばがんゲノムのように、基礎・臨床の壁を越えて、情報集約を組織的に実行するネットワーク形成を進めているケースもある。そこで、疾患ゲノム情報集約に関する脳科連としての合意形成を進めていくため、WGを設けることとなった。 WG3: 臨床データべースとAIを用いた解析(WG長:池田和隆(日本神経精神薬理学会)) 精神・神経医学や脳科学の加速的推進のため、ビッグデータである臨床データのデータベース化と、これに基づくAI解析が不可欠となると考えられる。加えて、臨床的には、患者当たり一回だけの横断的なビッグデータ収集だけではなく、コホート研究のような縦断的な繰り返しデータ収集と解析を組織化し、プレクリニカルバイオマーカーのスクリーニングや開発へ結実させていく必要性が高い。 WG4: 20年後,50年後の脳科学ビジョンの策定(WG長:林(高木) 朗子(新学術領域・次世代脳)) 脳科連の将来構想委員会の場において、プロジェクトベースの検討を離れ、中長期的にみた脳科学のビジョンについて、自由に対話をする必要性があることから、本WGが設けられた。 以上 |
||
| 2019年6月4日 | ||
第12回評議員会 |
||
【日本脳科学関連学会連合 第12回評議員会 議事要録】日時2019年5月19日(日曜日) 13:00~15:00 場所TKP品川カンファレンスセンター カンファレンスルーム4B 出席者(名簿順、敬称略) 欠席者(名簿順、敬称略) 事務局:理化学研究所 脳神経科学研究推進室 馬渕、八木、金居、孝子 配布資料資料1-1 第9回評議員会議事要録 参考資料:評議員名簿、役員名簿 議事(1)開会 (2)出欠確認 (3)連合代表より挨拶 (4)連合代表より活動報告 (5)脳科学将来構想委員会の活動報告 (6)脳科学リテラシー委員会からの活動報告 (7)広報委員会からの活動報告 (8)議決事項 (9)報告事項 (10)連絡事項 以上 |
||
| 2019年5月28日 | ||
平成31年(令和元年)度「戦略的国際脳科学研究推進プログラム」に係わる公募(1次公募) |
||
|
5月23日(木)より平成31年(令和元年)度「戦略的国際脳科学研究推進プログラム」に係わる公募(1次公募)が開始されました。 公募研究開発課題名: 締切は6月24日(月)正午です。 詳細は以下のサイトでご確認ください。 |
||
| 2019年5月21日 | ||
公募情報:平成31年(令和元年)度 「脳科学研究戦略推進プログラム」に係る公募について |
||
|
平成31年(令和元年)度 「脳科学研究戦略推進プログラム」に係る公募が開始されました。 公募研究開発課題名:認知症の予防・診断・治療法等の開発につながるシーズ探索研究 詳細は以下のサイトでご確認ください。 |
||
| 2019年5月17日 | ||
『知ってなるほど!脳科学豆知識』第13回「大人の揺りかご効果」を掲載しました。 |
||
|
『知ってなるほど!脳科学豆知識』第13回「大人の揺りかご効果」を掲載しました。 |
||
| 2019年4月26日 | ||
AMED 戦略的国際脳科学研究戦略プログラム(国際脳)および International Brain Initiative (IBI)の取り組みについて |
||
|
AMED国際脳事業およびInternational Brain Initiative (IBI)の取り組みをご紹介します。 |
||
| 2019年3月1日 | ||
第12回評議員会開催について(出欠伺い) |
||
|
2019年3月吉日
日本脳科学関連学会連合評議員各位
日本脳科学関連学会連合
代表 山脇 成人 日本脳科連関連学会連合 第12回評議員会開催について(出欠伺い)
日本脳科学関連学会連合第12回評議員会を下記の通り開催いたします。 ■日時 2019年5月19日(日) 13:00~15:30頃 第12回評議員会 15:30~16:00頃 第20回運営委員会 ■会場 ■議事 (旅費について) 評議員会、運営委員会ご出席にかかる旅費につきましては、会員学会にて支弁くださいますようお願いいたします。尚、ご所属学会での事務処理のために、本学会連合代表名義の出張依頼書の発行が必要な場合は事務局まで連絡をお願いいたします。 (出欠について) ※欠席される場合は、下記フォームをダウンロード後、押印された委任状を以下のいずれかの方法でご提出ください。 1. 本ページWEB上にアップロードにてご提出 (電子書面にて) (スケジュール)
【連絡先】 〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1
国立研究開発法人理化学研究所 脳神経科学研究推進室 日本脳科学関連学会連合事務局 担当:孝子(こうし)宛 |
||
| 2019年3月1日 | ||
第11回評議員会議事録を掲載しました。 |
||
|
第11回評議員会議事録を掲載しました。 |
||